
父から一昨日連絡がありました。私の管理していた旧アプリ開発用のApple IDは、削除ではなく「閉鎖」されたようです。私は過去に父親名義を借りて開発・配布したアプリケーションの管理をこれにて一切放棄します。
上のツイートをご覧の通り、私がかつて管理していたApple Account(旧名称:Apple ID)は「閉鎖」されたみたいです。これは一般的なApple Accountの「削除」のプロセスとは異なると感じたので、ブログで個人的にその使用を考察してみようと思いました。かつて某プログラミングスクールで「Apple IDはアプリを一度でも配信すると削除できなくなる」と聞いており、そのためにアプリ開発用のアカウントを用意させられましたが、実際にどうなるのかまでは教えてくれませんでした。
いくらアプリ開発者であってももいつかは管理できなくなる時が来ると思います。特に個人開発者であれば、アプリ開発者が死亡した後や、私のように管理維持が難しい・代替アプリが既にあるとなってしまった時が来るでしょう。個人のみならず企業であっても倒産してアプリ開発・維持の事業を撤退せざるを得ないときもあるかもしれません。そういった時に、私の情報が非力ながらも力になれば幸いです。
この記事では、一介の元アプリデベロッパーである私が管理していたApple Accountの「閉鎖」に至るまでのプロセスについてと、Apple Accountの「閉鎖」にまつわるUXの感想を紹介しています。
ただし、実は厳密には父親名義のアカウントであり、父親から又聞きした内容であるため、「閉鎖」の仕様がよく分かっておらず、「閉鎖」と鉤かっこ書きにしております。また、この記事もPV数が増えるようにZennやQiitaなどで公開せずドメインパワーのか弱いこの個人ブログにしか書いていないのは、やはり本当に閉鎖されているかどうかも不明であり、加えて「閉鎖」という用語が適切かどうかも分からないため、あくまで個人の意見であることを強調するためです。
アカウント「閉鎖」の背景
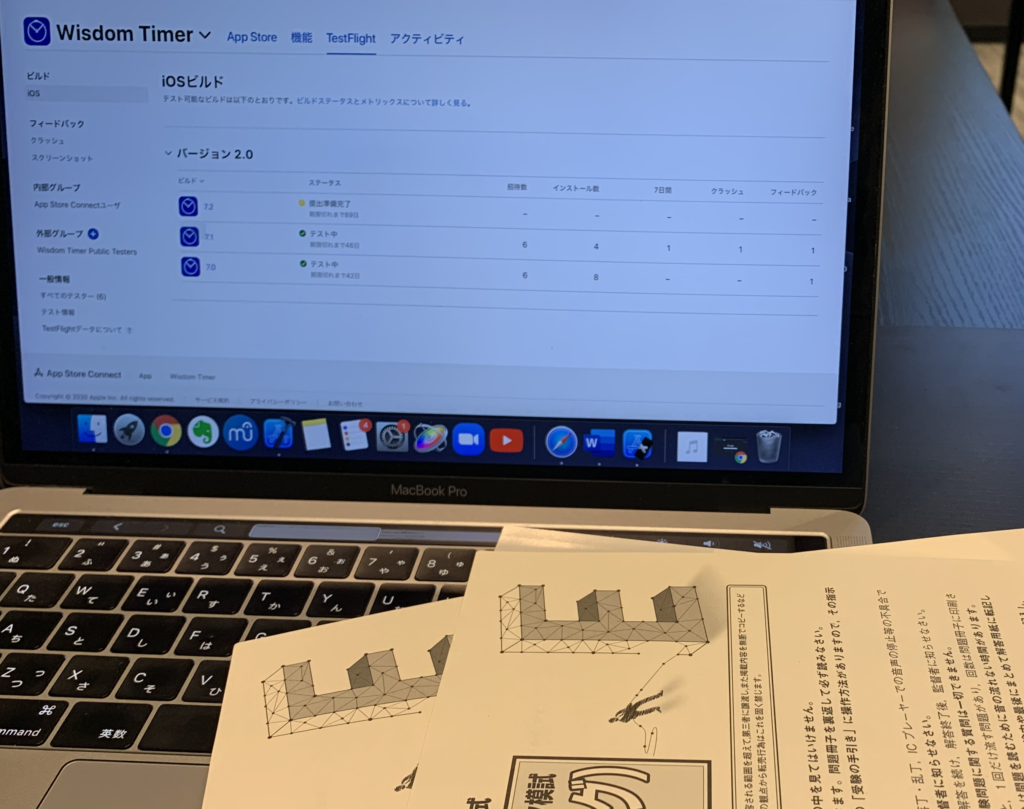
ことの顛末は、2019年2月にさかのぼります。当時プログラミングスクールに通っていて、App Store上で自前のアプリ「Wisdom Timer」を公開するためにApple ID(現:Apple Account)を開設し、そこからコロナ禍中も受験勉強の合間を縫ってアプリ開発にいそしみました。ただ当時高校生だったため、成年(少なくともこの時は20歳以上)でないと合法的なApple Developer Programの登録者(=Apple Developer Accountの保有者)とは見なされず、父親のアカウントを借りてアプリ開発をしていたのです。ところが、本当にやる気をもって開発できていたのは2019年ごろまでなんじゃないんでしょうか。
2021年以降は、どういうわけか吹っ切れて、アプリ開発はめっきり下火になりまして、主要な功績としては「BPM秒数チェッカー」iOS版を開発してiPadからリリースしたのみです。このアプリのリリースに関しては驚くほど、YouTubeの投稿に毛が生えたくらいに簡単でした。しかし、それはAppleの表の一面だったのです。
2022年6月、Appleの年会費と、iOSのアプリ開発に関する興味が冷め切っていたことを理由に、私が開発したすべてのアプリについて「サービス終了」を宣言し、アプリをストアから削除したうえで、アカウントを放置しました。Apple Developer Programは9月に無効化されました。
ステップ1: 削除を決意してから親に引き継ぐまで
時は過ぎ、2025年1月、同期の大学生よりも卒論をいち早く書き終え、卒業を控えた私は、Intelチップを積んだMacbook Proが大学用のBYODという役目を終え、完全にお荷物に感じてしまっていたころ、あのApple IDの存在が頭をよぎります。あのアカウントがある限り、僕はMacbookと前のiPhoneを捨てられない。さすがのApple、あれだけプライバシー保護を謳っているわけですから、アカウントを削除ないしは同等の状態にできるはずです。
Appleでは、「個人のデータやプライバシーを自ら管理いただく方策の 1 つとして、Apple では、その理由を問わず、ご自分の Apple Account をいつでも完全に削除できるようにしています。」と紹介されています。一般に、Apple Accountを削除しようとすると、「データとプライバシー」ページで、Apple Account にサインインし、「アカウントの削除をリクエスト」を選択し、本人確認の上削除(場合によっては「閉鎖」)という手続きを踏むことになります。
ところが、私の場合、Apple Accountのデータとプライバシー画面ではアカウントを削除できず、Apple Developer Supportに問い合わせるように案内されます。
そのうえ、Apple Developer Support最初に事情を説明した時にの名前で問い合わせたら、「恐れ入りますが、アカウントご本人様による問い合わせでないと削除リクエストは承れません」という趣旨のことを返信されました。これにより、私は、父の合意のもとではありますが、父のふりをしてメールでやり取りをしなければいけなくなりました。
ステップ2: 「閉鎖」という選択肢
Apple Developer Supportに父親の名義で改めて問い合わせて、加えて確認のために来たメールにもう一度「はい、アカウントを削除します」と送信すると、シニアアドバイザーの方が出てきました。
私は正直なので、父に電話を依頼することにしました。私は、さすがにどんな人でも音声データをごまかせないことをよく分かっています。
それで、メールでの日程調整のうえ、父に当該アカウントの認証デバイスを持たせ、シニアアドバイザーとの電話対応をしていただきました。
数日後。父曰く、『電話がかかってきた。法的な制約により、一度でもアプリを配信するとそのアカウントについては削除はできなかったが、この電話により閉鎖の手続きが完了したようだ、使っていたメールアドレスも解約してかまわない(シニアアドバイザーからの伝言を意訳)』との旨のLINEがかえってきました。親もよく分かっていないですが、どうやら「閉鎖」できたみたいです。
削除を決意してから「閉鎖」の通知が来るまでは3週間(調べる時間なども入っているので早ければ実質1週間強で終わるかもしれません)ほどでした。Apple社の対応はとても素早かったです。サポートも全て日本語で行われました。ありがたかったです。
ステップ3: 「閉鎖」の仕様の確認、最終的なログアウトとメアド削除
ところが、シニアアドバイザーがやってくれたらしい「閉鎖」の仕様がよくわからないんですよね。
そもそも、父はこの事象を「閉鎖」と伝えてきました。ところが、父はそういう方面の専門用語に明るくないため、具体的に用語として何と言っていたかを覚えておりませんでした。おそらく何か対応する英単語もあるんじゃないんですか。
まず、「閉鎖」したデバイスは普通にログインできています。削除や「閉鎖」(後述する無効化も)した後は、ログインできないものかと思いますが、新規デバイスや新規ブラウザからのログインはできませんでした。ので、今回通知したデバイスからログアウトすると、本当に誰もログインできないことになり、「閉鎖され」、一般利用者のように完全にアカウントの情報が削除されないながらも、アカウントが永遠に封印された状態となります。

例えば、webブラウザ上から「閉鎖」されたアカウントでログインを試みると、このように「本人確認を完了できませんでした。もう一度お試しください。」と言われます。無効なメールアドレスとして弾いていますね。これでアカウント管理者の死後・ないしは管理放棄後においても不正アクセスされるリスクを減らすことができます。一応削除と同等の効果が出ているようですね。
また、「閉鎖」されたアカウントであってもメーリングリストに追加されているためか、Appleからのメール配信をすべてオフにしていない場合では「閉鎖」されたアカウントのメールアドレスであっても「おすすめのアプリ」「Appleの新商品について」「Apple Developerからのメルマガ・WWDCに関するお知らせ」などのようなAppleからのメールが届きましたが、こちらはログインすることなくメール配信を止めることができます。同じアドレスでAppleアカウントを作り直すこともできません。
ちなみに私の場合はメールアカウントごと削除してしまうので大した問題はないかと思いますが、普段使いのApple Accountでデベロッパ登録をした場合など、「閉鎖」の手続きをすると、Appleから届くメールの解除など、アプリ開発を完全にやめてアカウントを削除するときの諸々の作業が著しく困難になるのではないかという懸念を抱いております。おそらくこれが私が通っていたプログラミングスクールでいわれた「Apple Developer用のApple ID (Apple Account)を取得するには専用のメールアカウントを用意した方がいい」と言っていた理由だと推測しています。私もこの主張には同意します。
そして、私は再びログインできるかの実験を行いました。このApple AccountがWebサイトでのログインで二度と使えなくなったことを確認しました。デバイスでは当該アカウントからログアウトしました。ただし、ログインしていたiPhoneからもう一度同じパスワードを入力すると、二段階認証も通過し、ログインしなおすことができました。この仕様こそ狭義の「削除」とは違う点だと思います。なお、この操作はデバイスを初期化してもログインできそうでしたのですが、万が一第三者にパスワードを突破されても(私の場合、電話番号のSMSの)二段階認証で通らないので、もうYahooメールも削除していいということなんだと思います。
「閉鎖」の仕様としては、このようにAppleデバイスからはサインインできてもWebサイトの方からはサインインできないということらしいんですね。まあもう過去の人の場合このアカウントの存在を忘れてますしこうなるくらいだったら結局放置する方がマシだと思うかもしれませんし、Appleの法的な管理報告義務があるので絶対に忘れられませんけれども、これがせめてものAppleなりのプライバシーへの配慮ということなのではないでしょうか。おそらく千年先もこのままなんでしょうね。日本や米国の法律にはあらがえないのです。
そして、初期化の後、私はYahooメールとパスワードの控えも削除しました。これで(Apple Developer死にアカウント管理用の)余分なAppleデバイスを一つ減らすことができるはずです。お疲れさまでした。
アカウント「閉鎖」に対する所感
これまで振り返って、謎な点については、その人が言う「閉鎖」の説明がアカウント削除として含まれており、サポートページにはあまり出てこないという点です。これはApple Accountのサポートページの説明が不十分であると言わざるを得ません。ほかにもApple Accountの使用停止処分については内部的に無効化、不正行為などが原因の凍結、自己申請or譲渡によるアカウント閉鎖などとの違いがはっきりしないです。もしかしたら無効化(deactivate)に近いのかなと疑ったりしましたが、アカウント再有効化用のコードは通知された模様は全くありませんでした。
なのでお客様向けには狭義の「削除」と「閉鎖」を一緒くたにしてサポートにおいては案内しているのかもしれませんね。個人的には「閉鎖」と「無効化」の違いも気になりますが、そんなこと気にする人なんていないんでしょうね。
また、削除においても無効化においても一度ログインするとアカウントにサインインしたり利用したりできなくなってしまうことから、閉鎖後のアップルアカウントの取り扱いの説明は酷似しているものと思われます。
今回、父から唐突にサポートに書いていない「閉鎖」という用語が出てきたことに驚きました。「閉鎖」の。このような概念・言葉の言い回しの違いというものは一つ間違えると信用にかかわるものですから、用語はサポートのヘルプページの時点でしっかり説明していただきたかったものです。そもそも「閉鎖」という用語自体シニアアドバイザーや父がでっち上げた用語の可能性があります。
というか、そもそも、Apple Developer Programにデベロッパー登録する時点で「お客様のApp Store等でのコンテンツの配信に伴い、Apple Accountは削除できなくなります(お客様の一部の情報は消せませんが、閉鎖はできます)」みたいなチェックボックスに同意するUIを用意してほしいですよね。もしかしたら利用規約をよく読んだら書いてあるかもしれませんが、そんなこといちいち確認しないし、そんな条項も何年・何十年も前に読んだきりで忘れている人も多いかもしれません。
なおこのような事象は、Apple Developer Program (App Store)のみならず、iTunes, Apple Music, Apple Booksなどでも同じことが起きると思われます。このようなプラットフォームでApple Accountでもって登録の上コンテンツ配信をされる皆さんはぜひ気を付けてください。
このようにApple Accountは、解約困難なサブスクの類いではないとは思うのですが、時には削除できないケースがあり、Appleはそれについての説明が不十分であったと感じます。これは伝達した父親の問題だけではないかもしてません。
この他にもAppleのアプリの審査は厳しいことで知られており、アプリのビルドのリジェクト率(非承認率)は決して低くはなく、最悪の場合不当にアカウントを凍結されることもあるかもしれないようです。
私は決してAppleがGAFAMの一角としてIT市場を牛耳ってる悪者だとは言いません。Appleには私がアプリ開発を始める前からお世話になってきましたし、これからも当分の間お世話になる予定です。別に敵意もありません。けれども今回の件を通して、Appleも完璧じゃなく、Appleという組織であるからこそ気付かない問題や、悪いユーザー体験を生み出す機構やバグがあるかもしれない、どんな企業も完璧ではないのだなと気付かされました。
ともかく、私は人生で二度と個人でモバイルアプリ配信はしないでしょうね。自分で開発する分には、モバイル対応のWebアプリや、Windows/MacなどにおけるOSSないしは有料配布ソフトであったり、Web上・サーバー上・埋め込みのソフトウェアの方がマシだなと思いました。



コメント